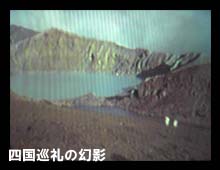|
●3
 老女や夫を苛む痴呆は、失禁、徘徊、奇行を招き、映像は生々しくも物語の中でそうした状況さえも乾きを持たせて切り取る。夫が老女の郷里に赴き、先祖伝来の墓の前にシャベルで穴を掘り自らを埋めようという下りは、
物悲しげながらに三國連太郎の乾いた演技が容赦なく心に突き刺さる。ただその演技の上手さが少し勿体ない気もする。この奇行をあくまでも痴呆による奇行と捉える場合は、痴呆が病気である以上、演技の尺度では測り得ない側面があるように感じるからだ。なぜなら、それは演技によるボケの胡散臭い部分が表出するからである。逆に言えば、扱いづらい部分は薄れているのやも知れない。いずれにせよ実際の痴呆を目撃してしまえば、その度合も理解できるのであろうが、やはりこればかりは現時点では断定できない。 老女や夫を苛む痴呆は、失禁、徘徊、奇行を招き、映像は生々しくも物語の中でそうした状況さえも乾きを持たせて切り取る。夫が老女の郷里に赴き、先祖伝来の墓の前にシャベルで穴を掘り自らを埋めようという下りは、
物悲しげながらに三國連太郎の乾いた演技が容赦なく心に突き刺さる。ただその演技の上手さが少し勿体ない気もする。この奇行をあくまでも痴呆による奇行と捉える場合は、痴呆が病気である以上、演技の尺度では測り得ない側面があるように感じるからだ。なぜなら、それは演技によるボケの胡散臭い部分が表出するからである。逆に言えば、扱いづらい部分は薄れているのやも知れない。いずれにせよ実際の痴呆を目撃してしまえば、その度合も理解できるのであろうが、やはりこればかりは現時点では断定できない。
 映像的には失禁という事実も、軽度の禁忌として受け付けてしまうところがあるが、映画では「オモラシ」のシーンが数回出てくる。初めての失禁に意識なく、正に幼児退行のように恍惚と微笑んでいる老女のシーン。一方、病院にて老女ではなく自分が漏らしていたと気付く夫が別の患者に嘲笑され情けない体裁を隠し切れない場面。夫が自白後、刑事の聴取を受けながら失禁してしまう場面など。実際に漏れている状態を取り込んでしまうのだから恐れ入るが、ブラックユーモアとして取ることもできれば、反面幾らでもシリアスになってしまう底無しに重苦しさが漂う映画なのだ。 映像的には失禁という事実も、軽度の禁忌として受け付けてしまうところがあるが、映画では「オモラシ」のシーンが数回出てくる。初めての失禁に意識なく、正に幼児退行のように恍惚と微笑んでいる老女のシーン。一方、病院にて老女ではなく自分が漏らしていたと気付く夫が別の患者に嘲笑され情けない体裁を隠し切れない場面。夫が自白後、刑事の聴取を受けながら失禁してしまう場面など。実際に漏れている状態を取り込んでしまうのだから恐れ入るが、ブラックユーモアとして取ることもできれば、反面幾らでもシリアスになってしまう底無しに重苦しさが漂う映画なのだ。
かくして老親が痴呆に冒されていく傍らで、息子の夫婦関係の縺れが、広報課に勤める息子が職場で出会ったイラストレーターの女と不倫するという形で映像上では表面化する。ただこの場面は、自宅のような閉鎖空間でない分箸休めになっているのか実に可笑しいのである。吉田喜重はかつて『戒厳令』や『エロス+虐殺』などでモノクロの映画を撮ってきた。しかし、この映画はカラーである。時代背景も8O年代の東京。息子が忍び逢うイラストレーターの女の部屋は、この映画公開後数年にして隆盛するトレンディー・ドラマで使われるようなワンルームマンションである。映像で色が確認出来る上に、打ちっぱなしのコンクリート内装、格子状の均整の取れたインテリア、間接照明、モダーン・リビング…とレイアウトされた部屋での会話は、 「じゃあ抱いてくださる」「君の胸、君の乳房を見ている」と間を持たせた軽薄短小に反撥する台詞満載なので、実に不釣り合いに思えて笑ってしまうのだ。時代性を求めようとしてもズボンを履き違えるとその分浮き彫りにされたシンボルの存在感で、あわやコメディーになってしまう危険性を垣間見た思いである。吉田監督には不敬至極だ
が、この映画で唯一、腹筋が緩んだ場面である。ただし、それでもやはり映画全体に通底する重苦しさは解かれず、時折部分で流れる死の<モティーフ>、水面に水藻がたゆとう姿、老夫婦が西国巡礼で阿蘇を歩く幻影や、当時自身も弁財天神社に帰依し、巡礼に関心を抱いていた細野晴臣の奏でる音像が一服の清涼剤を与えてくれる気がするのも、この映画が痴呆そして尊属殺人という至極シリアスな事象を扱っているからこその所以なのであろう。一貫して鈍色を基調とした状況描写がフィルムに刻まれ、映像は拭えない緊張と疲弊の彩りを隠し切れないでいる。 「じゃあ抱いてくださる」「君の胸、君の乳房を見ている」と間を持たせた軽薄短小に反撥する台詞満載なので、実に不釣り合いに思えて笑ってしまうのだ。時代性を求めようとしてもズボンを履き違えるとその分浮き彫りにされたシンボルの存在感で、あわやコメディーになってしまう危険性を垣間見た思いである。吉田監督には不敬至極だ
が、この映画で唯一、腹筋が緩んだ場面である。ただし、それでもやはり映画全体に通底する重苦しさは解かれず、時折部分で流れる死の<モティーフ>、水面に水藻がたゆとう姿、老夫婦が西国巡礼で阿蘇を歩く幻影や、当時自身も弁財天神社に帰依し、巡礼に関心を抱いていた細野晴臣の奏でる音像が一服の清涼剤を与えてくれる気がするのも、この映画が痴呆そして尊属殺人という至極シリアスな事象を扱っているからこその所以なのであろう。一貫して鈍色を基調とした状況描写がフィルムに刻まれ、映像は拭えない緊張と疲弊の彩りを隠し切れないでいる。
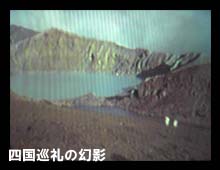
-4-
|